今春の定期あけぼのの廃止に続いて来春のトワイライトエクスプレスの廃止が発表されていよいよ終焉を迎える感のある寝台特急。今のところサンライズだけは残りそう。ここで寝台特急の廃止要因と豪華クルーズ列車にみる寝台列車の可能性を考えみてようと思います。
廃止要因としてはこれまで
A.利用客の減少 低迷
B.車輌の老朽化
が挙げられてきた。
では、利用者の減少の背景にあるものは何なのか?
A)
1.新幹線の開業
過去には新幹線が開業・延伸した時は昼行特急の廃止が相次いだものの、寝台特急は夜出て朝着けるという点で新幹線とはある意味住み分けができていたのだと思う。もっとも、新幹線の高速化でそのメリットが薄れたのも確かだろう。
2.格安ホテル
ちょっとした都市や街の駅前にはたいていビジネスホテルがあるもの。
時間さえあれば夜行に揺られるよりも格安ビジネスホテルのほうがゆっくり出来るというもの。確かに居住性や通信環境などは格段にイイと言えます。
移動手段も高速バスを利用すれば大幅に安くできますし、新幹線を使ったとしても寝台特急と比べて前述のメリットを鑑みて+αの料金でも利用価値があると言えるのではないでしょうか。
3.高速バス
安くて快適になった高速バス。新幹線の半額以下で東京~大阪を移動できるのは大きなメリット。ちょっとプラス(でも新幹線より安い)でハイグレードな車輌に乗れたり快適性は高まっています。かつての夜行列車と同様に夜出発して朝着けるので現地で朝から活動できます。一時期ツアーバスで問題にもなりましたが、それだけ需要があるとみていいと思います。
4.格安航空
LCCが日本でも飛び始めて1万円で東京と神戸など新幹線よりも早く安く移動できる手段が現れてきました。
安くて早いとなると遅くて高い寝台特急は夜に移動できるという点を除いて大きねメリットがなくなったと言えると思います。単に目的地への移動を考えるのであればLCCは選択肢としてかなり強い存在となると思います。
B)次に車輌の老朽化
現在寝台特急に使われている車輌はカシオペアとななつ星を除いて24系25型と国鉄時代に製造された車輌です。1973年からの製造で製造から30年以上、基本的な設計は更に前といえるでしょう。客車といえど長距離を走行する寝台特急なので痛みは小さくないでしょう。また、客車そのものが減ったことなど交換部品も少なくなってきていると言えます。
他に、客車列車が減ったことから旅客鉄道の機関車そのものが減っています。もちろん機関士もです。典型的な例がJR東海ですね。貨物は機関車がなければ仕事になりませんが、旅客鉄道では工事列車や臨時、寝台特急などを除いて機関車の出番はありません。JR東海さんはキヤ97などに置き換えて機関車を全廃しました。
(さらに…)
|
2014年5月29日 09:24|
カテゴリー:鉄道|
コメント
(7)
|
10月31日24時を持って閉鎖される赤川仮橋を約10年ぶりに渡ってきました。
前は大学1回の時なので2002年だったと思います。その頃の赤川仮橋は床板が木で隙間から水面が見えるという都会の橋では普通味わえないだろーという橋でした。 大阪らしく?その上を自転車が普通に走ってました。
大阪らしく?その上を自転車が普通に走ってました。
あれから10年。ついにおおさか東線の放出~新大阪の工事が本格化し城東貨物線の淀川橋梁も複線化が始まることになりました。これまで複線分の橋梁の片側を人道橋「赤川仮橋」として使用してきましたが、これで本来の用途として使われるようになります・・・めでたしめでたしとは言い難いのが現状。なにせ84年間も人道橋として利用されてきたので地域住民にとっては生活道路と化しているのです。市もなんとか人道橋を新設と考えたそうですが、財政難などで断念。閉鎖後は930m上流側にある菅原城北大橋を利用するようにとなっていますが、車ならいざしらず人と自転車には大変利用しづらい環境になりそうです。
訪ねたのは9日水曜日。台風24号が日本海を進み朝方は激しい雨と風になりましたが淡路に着くと次第に晴れてきました。予定では到着して直ぐに新座からの列車を撮れるはずだったのですが、中国道集中工事と中央環状の渋滞で遅れて橋到着前に目の前を走り去ってしまいました。そんでもって札幌からの臨貨もなかったようで来ず。結局昼の83レまで待ちました。平日&台風ということで同業者さんは数人ほど。 あとは橋が通れなくなるということでツアーのような感じで来られている方や元々近所に住んでおられた方など。鉄道ファンでなくても珍しい橋が渡れなくなるということで来られているようです。
あとは橋が通れなくなるということでツアーのような感じで来られている方や元々近所に住んでおられた方など。鉄道ファンでなくても珍しい橋が渡れなくなるということで来られているようです。
 右岸より伊丹着陸に入る全日空B787
右岸より伊丹着陸に入る全日空B787
(さらに…)
|
2013年10月13日 21:39|
カテゴリー:街・風景写真, 鉄道|
コメント
(0)
|
十和田観光電鉄も廃線の危機らしい
南部縦貫鉄道 栗原電鉄 日立電鉄 と東北北関東の鉄道が次々に廃線になっていく
少子化の著しい地域の鉄道はもう既に維持するのが困難な時期に差し掛かっているようだ。
鉄道の場合、維持費がかかる以上バスなどと比較して輸送量が求められる。
地方の過疎化しつつエリアでは維持するのは困難なのだろう。
どこかにあったが必ずしも鉄道が適しているというわけなく、バスでもバス停の整備や路線図マップやIC乗車券やお得なきっぷなどを提供することにより十分にサービスを向上させることは出来ると思う。バスであれば路線についても柔軟に設定できますし。
鉄道ファンとしては寂しくなりますが、ここは公共交通機関としてのあるべき姿をしっかり見据えて判断してもらいたいものです。
関連記事 河北新報 十和田観光電鉄正念場 沿線3市町の議会 支援に難色
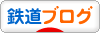

|
2011年9月4日 00:08|
カテゴリー:鉄道|
コメント
(0)
|
今日の神戸新聞に兵庫県の今年度と来年度予算に神戸電鉄粟生線活性化協議会への負担金を出さず予算もつけない方針と報じられた。
そして続いて、和田岬線廃線か?の記事
前者は国の方針と歩調を合わせたかのような政策に感じる。
どうも民主党政権は公共交通に対してはよく言えば厳しく、悪い言えば見識がないようだ。
どちらも鉄道と言う観点からいえば全力後進みたいな内容ですがそんなところでしょう。
よく言えば厳しくというのは、鉄道が公共交通としてオンリーではなく選択肢の1つとして捉えているのならば、公共交通の1手段でありその輸送需要・密度・地域性など環境からバスの方が向いていたり、バスでもコミュニティバスなどに転換した方がいいという結論もあるだろう。鉄道ファンとしては残念だけど需要の乏しい環境で存続させることは鉄道会社も営利団体である以上限界がある。勿論営利団体でなくても適正な規模というものがある。
では見識がないというのは・・・
一方的に高速道路を無料化して景気対策や地域活性化と謳う政策。
実験としては余りに影響が大きすぎ、環境の観点で見ても矛盾した政策。
車は経済を活性化させるほど裾野の広い産業と言うけれど、本当にそれでいいのか?
車を運転できない人が増えたときの足の確保は?
人口が減れば限られたパイの奪い合いになる。
神鉄もそうだが、ここにきて北近畿タンゴ鉄道も廃線の危機に瀕している。
直接の原因は舞鶴若狭道の無料実験ではないかと言われている。
国の実験の為に廃れてしまう・・・そんなことがあって良いのか 保証は?
和田岬線の話
実のところ地下鉄海岸線が建設されているときから既に廃線の話は出ていた。しかし、川重の甲種回送や利用者の便を図って電化したわけです。
そして地下鉄開通。明けてみれば地下鉄は需要を大きく下回る大赤字。この先はご想像で
もし本当に街の活性化プロジェクトで和田岬線が分断しているという意見が本物であれば悲しい限り。鉄道と人の距離が離れてしまっている証といえるのではと思う。個人的には和田岬線も含めたプロジェクトを計画が出来ないかと思う。例えばノスタルジックトレインとか、回旋橋を回るようにするとか。
今ままで一部ではファンはいたけども広く話題にならなかった分野が注目されてきたときって、どちらかというと本来あるべき姿が失われてきているときが多いように思う。広く鉄道が「日常」の生活の一部であり続けて欲しいと心から願いたい。
神戸新聞 利用客3割減 和田岬線の廃止検討 JR西日本
神戸電鉄・粟生線 11年度中に存廃判断へ
神戸新聞平成23年2月15日27面 県が負担金予算付けず
京都北部経済新聞 KTR一部路線廃止問題 9月までに結論へ 京都府
|
2011年2月16日 00:11|
カテゴリー:地域, 鉄道|
コメント
(0)
|
ついに明石海峡からもフェリーが消えるニュース
たこフェリー 姿消すのはほぼ確実 売却益を負債と従業員の退職分に当てるようです。
航路としては廃止ではなく休止なのがせめてもの救いですが、現状では遅かれ早かれ無くなる運命にあるでしょう
本来、明石淡路フェリー(当時 明石フェリー)は国道28号線の海上区間として県が運営しのちに道路公団が運営したこともあり明石海峡大橋の開通とともにその使命を終えるはずだったのです。
橋が架かる前は明石のフェリーの乗降場は大変な混雑でした。連休などになると待機場に入りきれない車が国道あたりまでの渋滞になるくらいで数時間待ちになるくらいでした。そのフェリー、私が気づいたときには既に民間の明岩フェリーになっていましたが、混雑は変りませんでした。今と異なり24時間運行を続けていました。

状況が変ったのが海峡大橋の大幅値下げと1000円高速。海峡大橋の弱点はその通行料金。そのことが原因で通行量は低迷し、そのころはフェリーも比較的減少も少なかったのです。しかしETC導入に伴う割引が始まってからは状況が変りました。橋の通行量そものの値下げとともに高速道路の割安料金、ついに1000円高速。高速道路の利用が大きくなると、料金が割高になり混雑する2号線を通ることになるフェリー経由は急減しはじめます。そのころは丁度そのほかの瀬戸内航路の廃止と重なります。そして今に至ります。

元を辿ると、国道フェリーとして開業し、そもそもがその代替として運行していた経緯を考えれば海峡大橋建設の時から航路廃止は決定事項だったと言えるのです。だからこそ明石海峡大橋の起工とフェリーの払い下げが同じ年に行われているといっていいと思います。言ってしまえば当時の公団の経営から見ればいずれ赤字・廃止になる航路なら先に払い下げるのは、後々起きるであろう問題を回避できる分当然の方針といえるかもしれません。

ただ、今現在の地域交通を考えれば、すべての船便をなくすのはどうかと思う。
そもそも、国道フェリーであり地域交通を担ってきた一面も考慮すれば、明石市や淡路側だけに押しつけるのは明石海峡大橋の利便性やそちらに力を入れてきた県にも責任はあるのではと思う。道は地上にある分だけで無いわけで海上の見えない部分も道そのもの。そうであれば県としても維持する努力は必要なのではないだろうか。
高速道路 整備新幹線 空港 通り抜け 平行在来線 飛ばない空港
グローバル化や高速化 大きな利便性の一方でミクロスケールの交通は議論されず切り捨てられてきた。
今こそマクロからミクロまでの交通政策を見直し、本当に必要であり求められるべき交通網を残していくべき時ではないだろうか。
関連リンク
明石淡路フェリー株式会社
神戸新聞 たこフェリー11月休止へ 明石‐淡路間
|
2010年10月17日 21:06|
カテゴリー:時事|
コメント
(2)
|






