鉄道
千葉県房総半島にある非電化ローカル線「久留里線」
今となっては首都圏で数少ない非電化路線でキハ30形、キハ37、キハ38と言った既にここでしか走っていない国鉄型気動車が現役な貴重な路線です。そんな路線ですが遂に置き換えが決まりまして、かつてキハ37が走っていた加古川線沿との縁を感じつつ訪ねてきました。

久留里線は内房線の木更津駅より始ります。木更津は千葉市から内房線に揺られて40分くらいの街。東京から千葉が総武快速線で40分ちょっとなので東京まで総武線直通快速で80分ちょっとでいける。距離が異なってくるが東京駅を大阪駅とすれば千葉が三ノ宮か神戸、木更津は加古川と言った感じだと思う。それは沿線の雰囲気からも感じ、東京から千葉は一面の市街地と住宅地の中を駆け抜ける一方、内房線にはいり蘇我を過ぎると浜手にはコンビナートや製鉄所の高炉が見えたりする一方、内陸側は住宅地もあるが田畑もそこそこあって郊外の様相を呈している。大阪から走ってきた新快速が大久保を過ぎた途端に田んぼと畑の中を走る感覚に似ている。
さて久留里線ですが、木更津駅を出発する線形も加古川線に似ていて加古川線が大阪側に向けて出発するのと同じく千葉側に向けて出発して分かれていく。乗車した列車は木更津駅9:15発上総亀山行き927D列車で上総亀山方からキハ38+キハ37の組み合わせ。乗車したキハ37の車内は地元住民のほか鉄道ファンや帰省客の姿も見られたものの長いロングシートにはまだ隙間も見られる状態であった。途中駅で徐々に減っていき途中の馬来田で目立って減った。途中横田で下り列車と交換。ついこの春まではタブレットの交換が行なわれていた。
 久留里線はほぼ全線が国道410号線と並行し何度か交差する。また、東京湾アクアラインや館山有料道路、首都圏中央連絡道路など道路網が急速に充実している。乗っていると分るが、キハが車と併走しても信号がない限り大抵は列車が抜かれていきます。列車そのものもエンジンの換装は行なわれて強力になっているものの、全力で走っている様な気配は感じられずのんびりとした感じが強い。
久留里線はほぼ全線が国道410号線と並行し何度か交差する。また、東京湾アクアラインや館山有料道路、首都圏中央連絡道路など道路網が急速に充実している。乗っていると分るが、キハが車と併走しても信号がない限り大抵は列車が抜かれていきます。列車そのものもエンジンの換装は行なわれて強力になっているものの、全力で走っている様な気配は感じられずのんびりとした感じが強い。
(さらに…)
|
2012年8月18日 00:10|
カテゴリー:交通, 旅, 鉄道|
コメント
(0)
|
青春18きっぷで西脇市と東京の往復に乗った列車です。帰りは大雨の影響で熱海から豊橋、米原から大阪のダイヤが乱れていた関係で列車番号や時刻が分からなくなっています。
8月12日西脇市から東京
西脇市1320S(普通)103系2両5:47発→加古川6:33着
加古川3202M(新快速)223系12両6:35発→米原8:56着
米原5110F(特別快速)313系8両9:14発→豊橋11:22着
豊橋〔列番不明〕(普通)313系4両11:25発→浜松11:59着
浜松786M(普通)211系3or5両(トイレなし)12:29発→興津13:59着
興津436M(普通)313系3両14:10発→熱海15:10着
熱海874M(普通)E233系15or11両15:18発→東京17:06着
東京→千葉 E217系
14日東京から西脇市
東京751M(普通)E231系7:53発→二宮9:09着
二宮755M(普通)E233系9:13発→熱海9:52着
熱海〔列番不明〕(433M30分遅れ島田行→静岡変更)313系10:16頃発車→静岡11:30着
静岡〔列番不明〕(浜松行続行)211系→浜松着
浜松〔列番不明〕311系4両→豊橋着
豊橋2535F(快速)313系15:03発→大垣16:31着
大垣241F(普通)313系4両16:37発→米原17:12着
米原813T?(普通 高槻から快速網干行き:20分以上の遅れ)221系12両→大阪着
大阪3513M(新快速:大阪始発に変更)223系12両19:30発→加古川20:23着
加古川1353S(普通)103系20:48発→西脇市21:26着
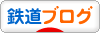
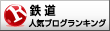
|
2012年8月16日 00:34|
カテゴリー:旅, 鉄道|
コメント
(0)
|
12日西脇市駅始発で東京経由千葉に行きます。
目的地は久留里線です。
1日目は千葉で1泊して、2日目は東京で1泊です。
|
2012年8月6日 21:00|
カテゴリー:イベント, 旅, 鉄道|
コメント
(0)
|
おおかみこどもの雨と雪の映画と小説を比較してみた。
前にも触れたように元々が映画の小説なのでほぼ小説の内容=映画の内容と言ってもいいのですが、細かな部分で言えば小説には映画では詳しく触れていない描写が存在しています。
ふ~と気づいた1つが話の本筋にはあまり関係のない部分ですが、串焼きです。
串に鶏肉とネギを刺して焼いてたべるやつです。わかりやすく言えば「ねぎま」みたいなものですね。私の好物でもあります。特にあの白ネギが美味しいんですね。もとい、作中では焼いた後で串をタレに漬けているのでネギマとはちょっと違うのかもしれません。小説ではこの串焼きについて少し詳しい描写があります。ちなみにネギマ(みたいなもの)・・・と言う表現は作中では正しくないかもしれません。おおかみおとこ・・・狼・・・イヌ科からご想像ください。イヌだけでなく猫にもダメですよ。
 話変わって、先日富山地方鉄道の通販サイトで「おおかみこどもの雨と雪」記念切符を注文しまして本日26日届きました。
話変わって、先日富山地方鉄道の通販サイトで「おおかみこどもの雨と雪」記念切符を注文しまして本日26日届きました。
(さらに…)
|
2012年7月26日 22:59|
カテゴリー:アニメ・コミック・ゲーム, 鉄道|
コメント
(0)
|
昨日の続きのような内容です。
昨日の文章の後半は中盤で地元の参加やファンの獲得について触れながら最終的に結論どっかに話が飛んでいたようなところがあったので改めて記そうと思います。
地方鉄道を利用する人を3つに分類してみようと思います。
1つに、「地元(沿線)住民」2つめが「来訪者」3つめが「(鉄道)ファン」としてみました。
ちょっと極端なのですがわかりやすいんじゃないかともいます。
今回はこの中で来訪者とファンについて考えてみようと思います。先に行ってしまうとこれが地元住民の利用にも繋がると考えられるからです。
来訪者 つまり沿線外からの利用者は路線沿線の観光地や買い物を訪れることを目的とする。わかりやすい例で言えば南海高野線の橋本より南の区間や元来の神鉄有馬線などがそうである。行楽地への旅客を見込んだり観光地に来てもらうために作られた路線です。いわばそれは路線が観光ルートになっていると言うことです。元々観光地的要素の強い地域では観光地までのルートや周遊エリアが定まっていたり、地域内での観光列車を走らせたりして鉄道など交通機関が自然と組み込まれていることが多い。
ではここで昨日あげた和歌山電鐵と伊賀鉄道はどうか・・・
いずれの路線も地域を巡るマップやスタンプラリーなどを駅で配布したりHPでダウンロード出来るようにして路線とともに地域のスポットや名所、名物を巡れるようになっている。特に和歌山電鐵は乗り放題切符とスタンプラリーを組み合わせるとともに、タマ駅長や楽しい電車と組み合わせて観光客を楽しませる工夫が出来ているところが好印象です。
鉄道を組み込んだ見て行って体感し楽しめるルート(マップ)を作りお客に提案するのは元々効果的だと思います。


(さらに…)
|
2012年7月12日 00:07|
カテゴリー:交通, 地域, 鉄道|
コメント
(0)
|
« 前のページ
次のページ »

 久留里線はほぼ全線が国道410号線と並行し何度か交差する。また、東京湾アクアラインや館山有料道路、首都圏中央連絡道路など道路網が急速に充実している。乗っていると分るが、キハが車と併走しても信号がない限り大抵は列車が抜かれていきます。列車そのものもエンジンの換装は行なわれて強力になっているものの、全力で走っている様な気配は感じられずのんびりとした感じが強い。
久留里線はほぼ全線が国道410号線と並行し何度か交差する。また、東京湾アクアラインや館山有料道路、首都圏中央連絡道路など道路網が急速に充実している。乗っていると分るが、キハが車と併走しても信号がない限り大抵は列車が抜かれていきます。列車そのものもエンジンの換装は行なわれて強力になっているものの、全力で走っている様な気配は感じられずのんびりとした感じが強い。



