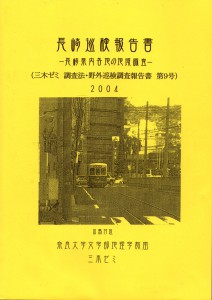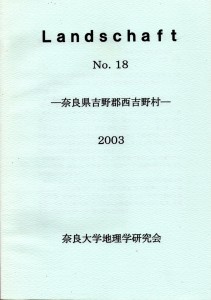18日午後にファイザーワクチン2回目を打ってきました。19日は軽くダウンしておりました。休みにしておいて大正解です。
若者の摂取が進まない云々と言われておりますが、現役社会人のウィークデイに打ったら翌日仕事になりませんよ。それは学生も同じ。結局週末とか休み前に予約が偏ればなかなか接種できないわけで。要は受けたくでも受けれないわけです。企業での接種と言われても大きなところだけで数が限られるわけですからね。分かってもらいたいものです。
話変わって
ドローンから巡り巡ってGISを勉強している昨今です。放送大学にGISの講義があるというので科目履修生として半期入学してみました。そんでもって初級レベルの数理やデータサイエンスやAIが学べる講座が在学中は8,000円→800円で受けれるというので申し込んでみました。まだ始めたばかりですが、なかなかに濃い。ぶっちゃけテキスト欲しいです。
というわけでGIS、Python、級レベルの数理やデータサイエンスやAI講座の3本立てで来年春まで頑張ろうと思います。
|
2021年9月20日 07:41|
カテゴリー:スキルアップ, 日記|
コメント
(0)
|
2018年12月16日17日疲れを癒しに箱根まで行ってきました。
ひとまずその時の写真を時系列で載せてみます。
 小田原
小田原

小涌谷小涌谷早川橋梁 小涌谷で行き違い
小涌谷で行き違い
(さらに…)
|
2018年12月29日 13:02|
カテゴリー:旅, 街・風景写真, 鉄道|
コメント
(0)
|
西脇市総合福祉センター荻ケ瀬会館北側の川下神社に加古川旧河道埋立の石碑と解説板がありました。内容は昭和初期から戦後にかけての西脇市内の加古川付け替えと埋め立てについて。かつての加古川は下戸田のあたりから和布町の北側を通り、今の西脇市総合福祉センター付近で杉原川と合流していたそうです。そのかつての河道付近ですが、今でもその痕跡らしきものが残っていました。



南側の和布町から旧河道に入る部分には1mほどの段差があり用水路が流れています。福祉センターの横の道はぐねっと曲がって坂となっています。また杉原川の河川敷からかつての合流付近を見てみるとどこか不自然な堤防の曲がりがあります。 グーグル・マップで見るとわかりやすいです。旧河道と思われる部分の区画がほかと異なっています。グーグル・アースでみると更にわかりやすく、やや曲線を描いた一定の幅の帯が東西に伸びています。
グーグル・マップで見るとわかりやすいです。旧河道と思われる部分の区画がほかと異なっています。グーグル・アースでみると更にわかりやすく、やや曲線を描いた一定の幅の帯が東西に伸びています。
[googlemap lat=”34.980627547891174″ lng=”134.97263634204865″ align=”undefined” width=”300px” height=”150px” zoom=”17″ type=”G_HYBRID_MAP”]西脇市和布町[/googlemap]
(さらに…)
|
2014年6月19日 21:25|
カテゴリー:地理|
コメント
(2)
|
先週は滝の音電車の音が最終乗り入れの可能性があったので朝から谷川にいたのですが、結局運用変更で4日が最後の運用になり、今週は下滝で撮りました。先週イマイチ甘かったのでリベンジですね。
合わせて流し撮りもしたのですが大きく失敗。本線みたいに本数が多いところで練習すべきですね。
いつもの2本の2734M快速大阪行きと183系こうのとり6号です。

2734M快速大阪行き

183系こうのとり6号
この前に来た4号も4両での運転となっていました。
このあとICOCAをチャージしに篠山口まで出ました。すると駅でJR西日本のお客様満足度調査の調査票を渡されましたよ。帰ってから内容を見ると普段篠山口を使っている人向けな質問が目立つのだけど、正直殆どこの駅使わないのでちょっと困惑気味だったりです。
さて、ICOCAをチャージをチャージして9時27分発の223系5500番台のワンマンカーで戻るまで少し時間があるので、向かいホームに停まっていた113系と留置中の223系5500番台を並びで撮影。 戻りの223系はほどよく乗った感じで発車。ワンマンなのに乗務員さんが乗って精算などの対応をされていました。本線だけでなく最近は福知山線でも女性乗務員が増えていますね。鉄道員のイメージもだいぶ変わりそうです。
戻りの223系はほどよく乗った感じで発車。ワンマンなのに乗務員さんが乗って精算などの対応をされていました。本線だけでなく最近は福知山線でも女性乗務員が増えていますね。鉄道員のイメージもだいぶ変わりそうです。
列車は川代渓谷を通過。下を見るとこんな感じです。 下滝の戻ってきてから前から気になっていた保存されている古い発電所を見に行きました。
下滝の戻ってきてから前から気になっていた保存されている古い発電所を見に行きました。
行ってみると、煉瓦造りで発電所としては小さい建物に「丹波市旧上久下村営上滝発電所記念館」のプレートが付けられた資料館になっていました。 一帯は丹波竜の発掘地で資料館には発電所の歴史とともに丹波竜についての資料が展示がされています。ちなみに資料は現在も小型の水力発電機をつけて館内の電気の一部をまかなっているとのことです。
一帯は丹波竜の発掘地で資料館には発電所の歴史とともに丹波竜についての資料が展示がされています。ちなみに資料は現在も小型の水力発電機をつけて館内の電気の一部をまかなっているとのことです。
周辺の篠山川は丹波竜の発掘地であると伴に、地形好き地理好きにはたまらない地形となっています。 太古の地層の露頭やポットホール、地層への溶岩貫入、断層などが見られます。見るのはタダなのですが、発掘地は保全地域になっていますので訪問の際はご注意ください。
太古の地層の露頭やポットホール、地層への溶岩貫入、断層などが見られます。見るのはタダなのですが、発掘地は保全地域になっていますので訪問の際はご注意ください。



|
2011年10月2日 22:07|
カテゴリー:地域, 街・風景写真, 鉄道|
コメント
(0)
|
多可町は基本的に兵庫県南部に位置しています。ですので基本的に冬場も大雪は滅多にありません。
そういっても北部に近いですので南部沿岸と比較すれば雪は多い方でしょう。
同じ多可町の中でも南北に長いですので天気は大きく変わります。
旧中町は南よりですのでそれほど雪は降りません。それはどちらかというと風上に笠形山などの山が多くあるのも理由かもしれません。
旧加美町の加美区は北に行くと極端に天気が変わります。中区でも真ん中を境に北はやや降りやすくなるものの加美区ほどではありません。

31日の場合、中区は昨日の雪と山の木々が白くなっている程度ですが、加美区も少し山よりの松が井の水方面に入ると写真のとおり雪で真っ白になります。

多可町加美区轟地区を望む
国道427号線筋は比較的雪は少ないですが、轟集落あたりより北は次第に雪が多くなってきます。特に清水(きよみず)より北は急激に積雪が多くなります。このあたりは山の反対側が生野方面に接して北部に一番近い領域になります。北西の季節風が比較的高い千ヶ峰などに雪雲がぶつかって雪を降らしているみたいです。標高が高く気温も低い上山が迫って日照が少ないですので降った雪が解けない条件もそろっています。

雪の大晦日 道の駅R427かみ
こうしてみると夏の天気も面白いですが、冬の天気も地形や風など夏とは違った状態が見れて面白いと思います。
ただし、ここに記しているように冬の内陸はちょっと行くと大きく天気や路面状況が変わりますので、無理の無い運転と滑り止めの準備をお勧めいたします。
くれぐれも安全運転で事故の無いようにお正月を過ごしましょう。
|
2011年1月1日 00:58|
カテゴリー:日記|
コメント
(0)
|
先日、私が奈良大学在籍時にお世話になった三木准教授(当時:助教授)からメールが送られてきました。何だろうと読んでみると、高校の先生から「2004年長崎巡検調査報告-長崎県内各地の地域調査」(三木ゼミ,2004年)を巡検の選定資料として使いたいという要望がありましたので、是非ともお役に立てればということで差し上げられたということでした。
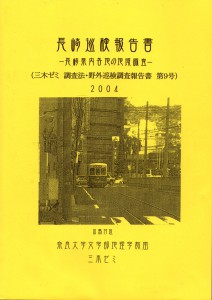
表紙は私のデザインです。もちろん写真もです。文字は当時の・・・です。
当時もそうでしたけど、まさか今になってそういう要望があると思っていなかったので驚きとともに、お役に立てればうれしい限りです。
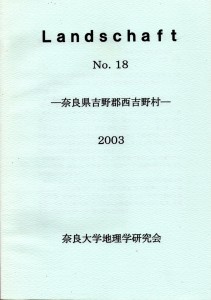
ちなみに奈良大学地理学研究会では研究結果として上の表紙のLandschaftを作っています。いましたなのかな。私が在籍していたときは2003年調査地の奈良県吉野具西吉野村(現 五條市)のLandschaftを作りました。西吉野村が五條市と合併してしまったので、今となっては西吉野村最後の報告書といってもいいでしょう。
西吉野村の調査については、その年の学祭で発刊したパンフレットが大好評で初日に無くなってしまうという事態になりました。そのパンフレットについては私の手元にも残りませんでした。結局翌年以降も増版して頒布していました。
元の版はあるはずなので要望があれば今年も印刷できるかもしれません。
もしその他、報告書や調査地についての資料など希望の際は奈良大学地理学研究会まで。多少時間がかかるかもしれませんが私に連絡頂いても大丈夫です。ちなみに報告書は毎年必ず発行している訳ではないですのでご要望にお応えできない場合もありますのであしからず。
奈良大学
奈良大学地理学研究会
奈良大学地理学研究会ブログ
奈良大学文学部地理学科
|
2010年8月1日 22:39|
カテゴリー:お役立ち情報, 諸々|
コメント
(0)
|
次のページ »
 小田原
小田原
 小涌谷で行き違い
小涌谷で行き違い